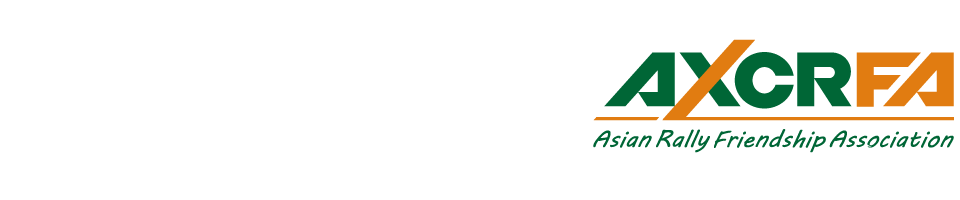LEG8
8月16日(土)パタヤ
四輪はチーム三菱ラリーアートが3年振りに王座奪還!
二輪は池町佳生選手が7年振り4度目の総合優勝!
2025年8月8日から9日間の日程で行われていた第30回アジアクロスカントリーラリーは最後のSSを終え、全ての競技を終了した。
四輪は ♯112 Team MITSUBISHI RALLIART の Chayapon Yotha / Peerapong Sombutwong 組が 三菱 トライトン で総合優勝を飾った。
チャヤポン選手は序盤戦、AXCRの生けるレジェンド ♯113 TOYOTA GAZOO RACING THAILAND の Natthaphon Angritthanon / Thanyaphat Meenil 組の トヨタ ハイラックスと激しく首位争いを繰り広げた。
ナタポン選手はLEG1で2位のチャヤポン選手に6分差をつけてトップに立つと2日目も危なげない走りで総合トップを維持。2019年まで7年連続優勝という金字塔は、そのほとんどが初日トップからの独走劇だっただけに、今年も「ナタポン選手が優勢」と予想する関係者も現れ始めていた。
しかしLEG3でナタポン選手のハイラックスはフロントサスペンションを破損して大きくタイムロス。ここでデイリー3位と健闘したチャヤポン選手が総合トップに立つと、後半戦に向け追いすがるトヨタ、いすゞ、フォード勢と生き残りを掛けた熾烈な戦いが始まった。
だが、今年のAXCRのコースはひと味違った。言葉では形容し難いほどタフだったのだ。激しい凹凸が延々と続き、その疲労がクルマや人を徐々にむしばんでいく。そしてあり得ない所が、あり得ない壊れ方をする…。この、近年希に見る「極悪路」の餌食になったのは、何もトヨタのナタポン選手だけではなかった。
LEG5では、チャヤポン選手を11分40秒差で追っていた総合2位の♯102 ISUZU SUPHAN YOKOHAMA LIQUI MOLY RACING TEAM の Suwat Limjirapinya / Prakob Chaothale 組の いすゞ D-MAX があらぬ姿に変形。SSアタック中にラダーフレームが折れてしまったのだ。もちろん、優勝圏外に後退してしまう。三菱の田口勝彦 / 保井 隆宏 組のトライトンも同様の理由でサスペンションアームが破損。LEG3で1時間以上タイムロスしてしまっている。それ以外にも多くのマシンが壊れていったのは、このレポートで連日お伝えして来たた通りだ。
こうして、ライバル勢の多くが "超" の付く極悪路の連続走行から来る金属疲労やトラブルによって脱落していく中、総合トップのチャヤポン選手もLEG5で深いぬかるみでスタック。脱出に時間を要し、トップの田口勝彦選手から12分遅れの9位に沈む、というアクシデントも起きていた。
ここで前半戦の不調から不死鳥のように蘇ってきたのが前年チャンピオンの ♯101 TOYOTA GAZOO RACING THAILAND の Mana Pornsiricherd / Kittisak Klinchan 組のトヨタ ハイラックスだ。
LEG3で1位、LEG5で2位と怒濤の追い上げを見せ、チャヤポン選手と14分差の総合2位に浮上すると、その後もLEG7で1位、LEG8で2位と連日の好タイムで首位を行くトライトンに追いすがったが残念ながら時既に遅し。LEG7以降も2位、5位と落ち着いた走りを見せた三菱のチャポン選手が7分51秒差で逃げ切り、栄えある記念大会での総合優勝を飾った。
チャヤポン選手はコロナ後に開催された2022年の「初優勝」以来、3年振り2度目の優勝。4度の挑戦で勝率5割、3位1回という素晴らしく安定感のある実績を残してみせた。また、三菱は喉から手が出るほど欲しかった「新型トライトンによる栄冠」を手中に入れることができた。
これが、今年のLEGごとの総合順位の変動だ。チャヤポン選手は中盤以降、安定して首位に立ち続けたように見えるが、中盤以降、尻上がりに調子を上げていく ♯101 マナ選手との戦いは凄まじかった。マシンの挙動も良く、互いの闘志が乗り移ったかのような、鬼気迫るバトルは圧巻だった。
ここで注目しておきたいのが、♯142 Feeliq Innovation Motorsport の Bailey Cole / Sinoppong Trairat 組だ。彼らのフォードラプターは、市販車をベースに、改造範囲が厳しく制限された車両「T2A」なのだ。改造クロスカントリー車両「T1」が上位にひしめくリザルトの中で、T2Aによる総合3位の成績はひと際輝いて見える。
ベイリー・コール選手はAXCRでは珍しいアメリカ人ドライバー。今回、フォードチームのオファーに応じて北米からスポットで参戦したプロのオフロードドライバーだ。初出場のベイリー選手は初日、26番手スタートながら11位のタイムでフィニッシュするとその後も総合順位を上げ続け、ついには総合3位の栄誉を手にしてしまった。
デイリー順位を追ってみると、11位、8位、4位、5位、8位、7位といった具合。大柄なラプターで走るジャングルの道は、広大な地平を走るアメリカンデザートレースとはさぞ違って見えたことだろう。だが、この荒れた路面で逸ることなく、クルマの限界を引き出しながらよくこれだけ丁寧に、そして速く走りきったものだと思う。
いずれにせよ、ベイリー選手はアメリカンレーサーが東南アジアのジャングルで通用することを、そしてフォード ラプターが想像以上に頑丈だったことを、我々に証明して見せてくれた。
話をチャヤポン選手に戻そう。時は最終日の最終SSの直前だ。朝のロードセクションを終え、セレクティブセクションの入り口に到着した40台近いマシンがスタート順に待ち並び、ドライバーやナビゲーターが最後の空気圧調整を行ったり、メカニックやメディアと話したり…。スタート前の、いつもの和気あいあいとした光景が広がっていたが、スタートラインに立つ チーム三菱ラリーアート 増岡浩総監督の目だけは鋭く、はるか彼方をジッと睨み続けていた。
実はこの時、チームの命運を託したチャヤポン選手のトライトンが、RSの途中でストップしてしまっていたのだ。昨年終盤に起きた首位陥落の悪夢が、三菱関係者の脳裏をよぎる。いや、故障車を追い抜いたほぼ全てのドライバーとコ・ドライバーが、三菱の2年連続の不運をほぼ確信していたことだろう。なぜなら、スタートがもう2分後に迫っていたから。
だがその時、1台の赤いマシンが風のように現れた。
後を走っていた三菱チーム3台目のトライトン、小出一登/千葉栄二 組が現場に到着し、原因を特定。修理を施して112番は息を吹き返したのだ。なんと水回りの、単純なトラブルだった。
だが試練は続く。最終日だけは前日のタイム順ではなく、総合順位でのスタートだ。チャヤポンは♯101 マナ選手のハイラックスの前でスタートしなければ、RSのタイムオーバーでペナルティが与えられてしまう。
チャヤポン選手の心臓はもう、口から飛び出す寸前だったに違いない。そして待ち受けるマナ選手も「ライバルはもう現れない」と思いかけていたいたことだろう。だが…奇跡は起きた。オフィシャルの時計がスタート1分前を指した時、♯112のマシンが♯101 のマシンの前に滑り込んだ。
「サーティセカンド、テンセカンド、ファイブ、フォー、スリー、ツー、Go!」。チャヤポン選手は矢のような速さで飛びだして行った。
「心臓に悪い…。まあ、最後60kmくらい、走って来てくれるでしょう!」
苦笑いする増岡監督の目に、笑みが戻っていた。
そしてゴール後のサービスエリア。何度も何度もクラクションを鳴らしながら入って来たチャヤポン選手はサービスクルーの前に停めるやいなや、コ・ドライバーのピーラポン選手と一緒にトライトンのルーフによじ登った。そして、沢山の寄せ書きが集められたラリーアートの旗を天高く掲げ、大きく振ってみせた。チーム三菱ラリーアートのピットはもう歓喜の渦だ。増岡監督の目にも小さく涙が光っていた。
「成功は一人の力から生まれるものじゃない。すべてはチームワークから生まれるもの。僕たちはチーム三菱ラリーアート!!」後日、SNSにそう投稿したチャヤポン選手のせいいっぱいの気持ちが、掲げる旗を握る小さなガッツポーズに込められていた。
そしてこの日は Chayapon 選手の誕生日でもあった。ゴール2km手前でエンジンがストップしたあの忌まわしき日から丸1年。悔しさをバネに、今年はチームと自分自身に最高のプレゼントを贈ってみせたのだ。
なお、四輪のチームアワードは1位が Team MITSUBISHI RALLIART(♯105, 112, 118)、2位が TOYOTA GAZOO RACING THAILAND (♯101, 113, 133)、3位が ISUZU SUPHAN YOKOHAMA LIQUI MOLY RACING TEAM(♯102, 103, 110)となっている。
王者トヨタとがっぷり四つで渡り合い、正々堂々と勝利したチーム三菱ラリーアート。この1年はエンジントラブルを巡る反省から始まり、高出力と高耐性を両立するセットアップを探り、試行錯誤を繰り返す毎日だったという。そしてAXCRで大切なナビゲーション技術をも磨くべく、現地での訓練も敢行。「新型トライトンで挑戦3度目の正直!」という背水の陣で挑んだ2025年。彼らの努力は見事に実を結んだ。そしてチャヤポンという若くエネルギッシュでクレバーなヒーローをも生み出した。
だがそれ故に、ライバルチームとは紙一重の勝負であったことも間違いない事実だろう。年々速くなる競技スピードと史上稀に見る極悪路。このふたつが重なった30周年記念大会で見えたものは、「どんな悪路でも壊れないマシン作り」「どんな悪路でも壊さず速いドライビング」そして「どんな難コースでも迷わないナビゲーション能力」が高次元に融合された "新しいクロスカントリーラリー" の姿だった。
アスファルトにダートにマッドにロックに砂。幾度も繰り返す川渡りに延々続くウォーターベッド。こんなに路面が変化するラリーが他にあるだろうか。こんなに激しい凹凸が延々と続くラリーが他にあるだろうか。こんなにも天気が変化するラリーが、そしてこんなにも人間的なラリーが他にあるだろうか。
止む無きキャンセルがあったとはいえ、2,500㎞近く続いた千変万化の道を越え、ゴールまで走り切った全てのエントラントに、そして惜しくもリタイアとなった全ての挑戦者に敬意を表したい。
光陰矢のごとし。長いようであっという間に過ぎ去った30年。AXCRはひとつの節目を越え、また新しい時を刻んでいる。主催者も今年カンボジアに渡り、プノンペンに行けなかった悔しさは忘れてはいない。無念にも参加を断念したカンボジアとベトナムの友人達もきっと待ちわびていることだろう。来年も変わらず、雨期まっただ中で行われるこのアジアクロスカントリーラリーを、お楽しみに!
Moto
総合TOP10内に日本人選手が6名。例年より長丁場のはずが、終わってみればあっという間の8日間
ついに最終日を迎えた大会8日目、LEG.8の朝は激しくは無いものの昨晩からの雨が降り止まず、SSのルート前半に設定された湖畔沿いをなぞる赤土のフラットダートはしっとりと水分を含み、ライダーたちの出走を待っていた。雨期のタイでは毎晩のように雷を伴う雨が当たり前なのか、夜が明けると不思議と徐々に雨脚が弱まり、昼頃には強い陽射しが流れる雲の合間から降り注ぐ。
タイ王国の未舗装路の地面のことを「赤土」と表現することはもはやお決まりだが、それは一度見れば納得できるのではないだろうか。本当に「赤い土」という言葉以外思い浮かばない、赤レンガ色で細かい砂利混じりの道路がずっと続いている。
午後にフィニッシュセレモニーが控えているため、やや短めの総走行距離約327kmとなるこの日、うち約120kmがSSに設定され、前半約60kmは右手にときおり湖面が視界に入りつつ、直線と緩いカーブや直角カーブが次々と現れるルートだった。起伏が無く単調のように思えるが、これがスロットルワークと荷重移動、ステップワークなどで明確にマシン操作が手に取るように分かる、ライダーにとっては楽しいフィールドとも言える。
この赤土路面の特徴のひとつとして、濡れていてもグリップする部分と、まったくグリップしない、まるで鉄板にべっとりとグリスを塗りつけたような部分があることが挙げられる。
これは砂状かパウダー状かによるのではないかと思われるが、パウダー状の土は乾燥状態ではファンデーションのように細かく軽い粉がカチコチに固まり、タイヤに削られると砂埃となって舞い上がり、いつまでも空中に漂う。逆に水分を含めばネチョネチョでヌルっとしたペースト状に変わる、と言えば想像できるだろうか。
濡れた赤土のダート路面では、砂状か粉上かが見た目ではなかなか分からないものだから、とくに速度を上げる場面では厄介なポイントとなる。そんななか、撮影ポイントで待ち構えるカメラの目の前をアグレッシブに駆け抜けて見せたのが、スマティ選手(#17/Team Musashi International/KTM 250 XCW)と、日本から2度目の参戦となる泉本選手(#22/TEAM JISOK-RR/HUSQVARNA FE450)だった。実際、2人の区間タイムは他者より数分差をつけている。
両者以外に、逆ハン(ハンドルを逆に切ってのコーナリング)を切って見せてくれたライダーはいなかったように思える。これが「絵的」にダイナミックで撮る側としてもテンションが上がるというもの。ちなみに泉本選手は毎日ホイールのワイヤーの張り具合チェックに余念が無かったが、1本折れてしまったらしい。それだけ激しく負荷が掛かっていたということなのだろう。
SS後半は広大な森とプランテーションの間を駆け抜けるラフロードで、タイヤがすっぽり沈むほどの「水場」もしっかり用意されていた。
さて、大会最終日の順位(総合)を見ると、連日上位を競っていた面々が並ぶカタチとなった。
初めてアジアンラリー(Asia Enduro)に参戦したのが2001年という池町選手(#16/Team Musashi International/HUSQVARNA FE350)が自身4度目となる総合優勝を果たし、母国タイ王国出身の王者ジャクリット選手(#46/JC DIRT SHOP/KTM 500 EXC-F)が2位、同じくタイ王国出身のスマティ選手(#17/Team Musashi International/KTM 250 XCW)が3位、そして4位変わらずの泉本選手(#22/TEAM JISOK-RR/HUSQVARNA FE450)、5位には昨年優勝者の松本選手(#1/Indonesia Cross Country Rally Team/KTM 250 EXC-TPI)と続く。
詳細は公式リザルトを確認してもらうとして、上位10名のうち6名が日本からの参戦者という結果となった。前述の選手だけではない日本人の実力者たちが名を連ねている。
今年は30周年記念大会ということもあってか、日本からの参戦者が非常に多く、もちろん初もいる。すべてを終えてアジアンラリーの印象を尋ねると、「また来たいという人の気持ちが分かりました。この祭りのような雰囲気は他では味わえない、とても楽しい。もちろん、モンゴルやアフリカのラリーも楽しいですよ。それぞれ魅力があっていいですよね」と満足そうに話す。
国内外のラリー経験が豊富な参加者は、「やっぱ競い合える仲間と走るのが好きだから、そんな場所があって、一緒に行く仲間がいたらまた参加したいですね」と語る。
本来であれば8日間の競技だったところ、諸事情により2日間の休息日を挟むことになったが、その件について言及する者もいた。
「ちょっと消化不良な部分はあるが、仕方ない。モトクロスのような短時間全力で戦う競技と違って、ラリーは数日間ライダーとマシンに負荷を掛け続けることで勝負に差がつくもの。脱落者が出てくるなか走り続けることで勝ちにつながるわけで、休息日があったことでその負荷が抜けてしまったことは残念。そこはもっと上位に行けたと思う」
1996年から続くアジアンラリーには初期頃から関わってきた参加者の1人は、年齢的に今年が最後だと言う。そもそも70歳をとうに過ぎていながらこの過酷なラリーに参戦し続けていることも驚異的だが、ほぼ毎年クラッシュしては怪我を負い、ときには現地病院へ搬入され、しばらく入院ののち帰国し、日本で手術と治療生活を送ってきたという経緯もある。
周囲の仲間からは「今年は絶対に怪我しないでくださいよ!」「死んだらコ●す!」など冗談交じりで本気で心配する声も多かった。
自ずと参加者の中にはリピーターやベテランが多くなる一方で、今年は初参戦でそもそも競技ラリーも初めてという挑戦者が現れたことも新鮮な出来事だった。
独特な雰囲気を持つアジアンラリーは他の競技ラリーとはだいぶ趣が異なるが、競技であることに変わりはない。「楽しい」だけではけして本当の意味で楽しむことは出来ないだろう。
実際、そんな厳しさを内包しつつ、しかし参戦への「敷居の低さ」はとても重要なこと。自前のバイクとエントリーフィー(ここがキモ)、そして長いお盆休みを確保すればアジアンラリーへのトビラは開かれる。
30年も続けばその間に人も国も政治も変わるというもので、それは本大会にも言えることだろう。この先もタイ王国を中心としたクロスカントリーラリーがライダー(もちろんドライバーも)たちのチャレンジスピリッツを刺激し続けることを願いつつ、終わったばかりでもう来年の開催に期待が膨らんでしまう。
本サイトでは過去のレースの模様をブックレット形式で読むことが出来る。そちらも是非チェックして欲しい。
(文・写真/田中善介)