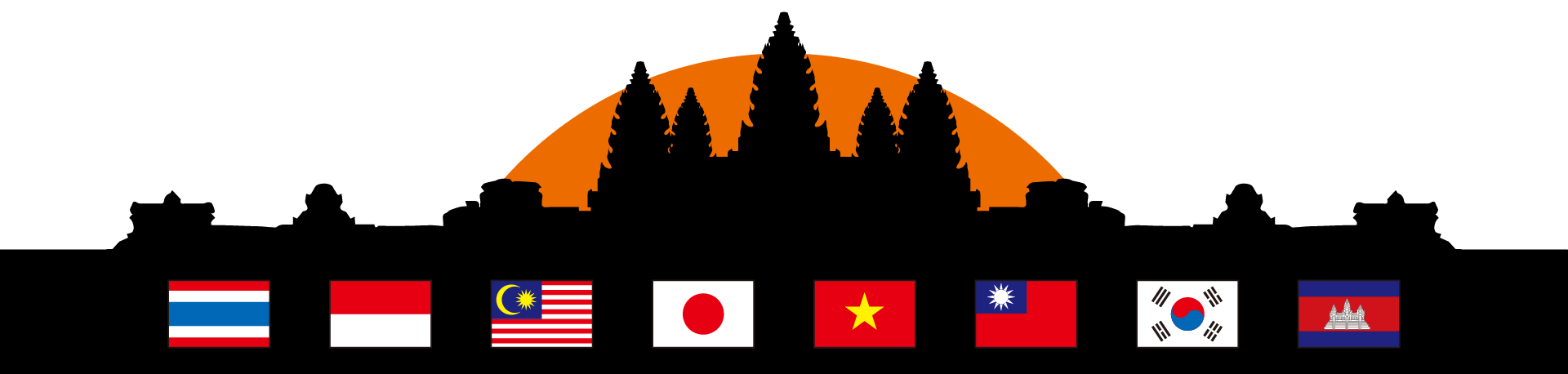11月21日(月)晴れ ブリラム
LEG 0
実に3年3か月ぶりのセレモニアルスタート!
2022年アジアクロスカントリーラリーが開幕
1996年の第一回大会から27度目の開催となるFIA公認の国際ラリー「アジアクロスカントリーラリー」がタイ王国の東北部、ブリーラム県のチャーン・インターナショナルサーキットにて開幕した。
ここ数日はっきりしない天気が続いたブリラム。だがこの日は違った。朝から青空が広がり、11月も終盤だというのにTシャツ1枚でも汗ばむほどの熱気だ。
7時には公式車検がスタート。「車検に通るかどうかが何よりも不安だった」という♯132 夷藤新基 / 里中謙太(eArk sports WRT)のスズキ ジムニーが真っ先に飛び込んで来た。
今年は4輪が20チーム31台、2輪が16台、サイドカーが2台、そしてアドベンチャークラスの1台を加えて総勢50台と、イレギュラーな時期の開催にも関わらずなかなかの台数が集まっている。選手の国籍も日本、カンボジア、韓国、マレーシア、タイ、台湾、ベトナムなど多岐にわたっている。
4輪はワークス勢がひしめく熾烈な戦い
4輪の注目は初参戦の Team Mitsubishi Ralliart だ。ダカールラリーで2度の総合優勝を飾ったレジェンド、増岡 浩氏(MASUOKA Hiroshi)を総監督に、ピックアップトラック「トライトン」の3台体制での挑戦だ。ドライバーはタイとインドネシアの若手選手。現地にも大勢の関係者らが駆けつけ、往年の「ラリーアート」ブランドの復活を掲げたチームの士気はとても高い。
これに真っ向から対抗しているのが Toyota Cross Country Team Thailandの ハイラックス レボ 勢だ。2019年まで激闘を繰り広げてきた因縁のライバル、いすゞ D-MAX勢との戦いを実力で倒し、新進気鋭の三菱勢も経験力の差で一気になぎ倒いてしまおう、という意気が感じられる。
だがここ数年ひたすらトップを走り続けてきた王者いすゞも負けてはいない。タイ人の力を結集した Isuzu Suphan Explorer Rally Team は D-MAX 3台の体制で参戦。トヨタや三菱が台頭する新時代の戦いでもチャンピオンの座を守るべく、静かに闘志を燃やしている。
これらメーカーワークスの三つ巴の戦いに楔を打ち込もうとしているのが Raptor Team Thailand の フォード ラプター勢だ。また、日本の SRS-Osaka Welport Rally Team は、昨年モデルチェンジしたばかりの新型ランドクルーザー300がいち早くラリー車に改造。世界のランドクルーザーがラフロードで見る走りも注目される。
また、最近ルマンでも活躍するようになってきたクルマ椅子ドライバー青木拓磨選手(Fortuner GEOLANDAR takuma-gp)が参戦15年目にして初の2台体制を構築、悲願の初優勝を虎視眈々と狙っていることにも覚えておきたい。2号車の塙 郁夫 選手もバハなど北米のデザートレースを中心に幅広く活躍しているベテランドライバーだ。
LEG1のスタート順を決めるスーパーSS
午後からはラリーのHQ(ヘッドクォーター)からほど近いエリアで、ターマック(舗装路)を封鎖してタイムを競うスーパーSSが行われた。これは3kmという短い距離ながら、その結果によって翌日のSSの出走順が決まる重要な戦いだったため、2輪の選手も4輪の選手もみな、真剣な表情で臨んでいた。中にはターマックの走行に備え、マッドタイヤからATタイヤに履き替えていたチームもあったが、その結果は貼付の表をご覧いただきたい。
とはいえ、わずか3kmのタイムから5日間/1500km先のゴールを占うのはまだ難しい。最終日に辿り着くアンコールワットの眼前でいったい誰が笑い、誰が涙に暮れるのか?
夜8時からはチャーン・インターナショナルサーキット前の広場でセレモニアルスタートが行われ、全てのマシンが華々しく出走していったが、2022年アジアクロスカントリーラリーはまだ始まったばかり、今後のレポートをご期待ください!
(写真/高橋 学・文/河村 大)
moto
独特の雰囲気が漂うMOTO部門、あの時の空気が帰ってきた
MOTO部門のエントリーリストには、18人の名が連なっている。しかし現地にやってきたのは若干少ない10数名。チーム丸ごとキャンセルもまた、まだコロナ禍にあることを実感させるものだ。
そんな中、日本からはMOTOが8名、SIDECARが4名(2台)がエントリーし、全員がタイの大地に降り立った。じつはなかなかの大勢力だ。ほか、カンボジア、インドネシアなどからもやってきた。
車両メーカーでは、KTM、ハスクバーナ、ホンダ、ヤマハ、スズキ、GASGASなど、現行モデルをはじめすでに絶版となった機種も揃う。排気量では250~350ccクラスが主だが、790ccのビッグバイクでタイの赤土に挑む強者もいる。
LEG0とされる、LEG1の出走順を決めるスーパーSS当日。そんなMOTO部門の様子はというと、朝から車検を受け、搭載が義務付けられたGPSドライブレコーダーシステムの取り付けに難儀している場面がチラホラ見られた。バイクは何かを取り付けるスペースが、4輪と違ってとても限られているのだ。
この日は車検、3km弱の短いスーパーSS、そして夜のセレモニーがあるのみ。ひさびさのアジアンラリーで、オーガナイザーが準備したウオームアップの日、といったところだ。
もっとも人数が多い日本人参加者を見ると、過去何回かの参戦経験者にとって、3年半ぶりのアジアンラリーは「待ってました」「ようやくだね」という「ここに帰ってきた・戻ってきた」感が印象的だった。そして「久しぶりだからね、無理はしないよ~」と口にしつつも、翌日のルートが記された、ボリュームたっぷりの太巻きのようなコマ図を受け取り、じっくりチェックして蛍光ペンでマーキングし、電動のマップホルダーにセットする際、ジー……というモーター音と共に、身体に染み付いた「あの時」の記憶から表情が徐々に切り変わっていく、そんな様子だった。
新規の参加者もいる。数年前にチャレンジする予定がコロナの影響で今年になった、仲間に誘われてやってきた、というものだが、いずれも「ベテラン」というわけでもないらしい。
無理さえしなければ、オーガナイザーが用意したアジアの舞台で極上の海外ツーリングを味わえる。その一方、何があるか分からない、どうにもならない、どうしようもない、という洗礼が待っている。ライディングスキルやテクニックも完走への大きな要素だが、特に1人で走るバイクの場合、ラリーならではの「人間力」が問われることの方が大きい気がする。そこではベテランもビギナーも等しく、それもまた醍醐味なのだ。
そして注目が集まるサイドカー部門では、「サイドカークロス」という、モトクロスコースを走る専用フレームにハスクバーナのエンジンを搭載したオリジナルマシンが1台、そしてもう1台はロシア製の「ウラル」だ。アジアンラリーにサイドカーが参戦するようになり、その物珍しさとチャレンジ精神に、2輪・4輪関係なく、多くの関係者からも熱い視線が注がれている。
参加すれば、1人ひとりがそれぞれドラマに見舞われる。終わってみればまた行きたくなる。この3年間で味わった「アジアンラリー・ロス」が、ついに晴れる時がやってきたのだ。